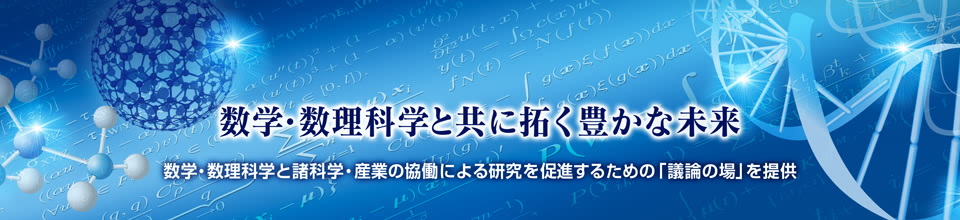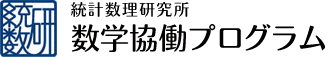|
|
「数学協働だより」
数学協働プログラムでは、メールマガジン「数学協働だより」を月一回発行しております。 送信用メーリングリスト: ann-coop-math@ism.ac.jp 購読希望の方は coop-math-sec@ism.ac.jp にメールのタイトルを「数学協働だより購読希望」としてご連絡ください。
(2015年10月号より、PDFファイルによる配信を実施しております。) (2015年5月は休刊です。)
☆数理・生命科学作業グループからの「提言書」 2015年3月23日、「数学連携ワークショップ~生物学と数理科学の協働~」@日本数学会2015年度年会にて、数理・生命科学作業グループより 「数学協働プログラム提言『数理生命科学』」 が公開・配布されました。この提言書では、数学が生命科学の様々な分野において既に多岐にわたって利用され、分野の基礎となっている現実を紹介すると同時に、これから分野の発展に寄与すると考えられる数学的手法や視点についての情報を提供しております。 現在、下記URLにて一般公開しております。 http://coop-math.ism.ac.jp/info/coop-math-life 皆様の活動の更なる発展に繋がれば幸甚に存じます。
☆数理材料科学コミュニティ 2015年2月9日、数理・材料科学作業グループにおける議論を基に、「数理材料科学コミュニティ」の運営を開始いたしました。 http://coop-math.ism.ac.jp/info/MathMate-comm 数学・数理科学分野と物質・材料科学分野の協働による研究活動に関心をお持ち の方々にとって、様々な活動の情報を気軽に発信・共有するための触媒となり、 異分野間の共同研究や開発、新研究課題や学術分野の萌芽など、皆様の活動の益 々の発展に役立てていただく事を目的としております。 関心をお持ちの方はぜひ上記サイトをご覧ください。
SNSサービス 実施中! 数学協働プログラムでは、Facebook, Twitterでの告知も行っております。数学協働プログラムの行事だけでなく、協力機関の異分野協働関連行事も宣伝しております。ぜひフォローおよびシェアをお願いいたします。 数学協働公式Facebook : https://www.facebook.com/CoopMath 数学協働公式Twitter:@CoopMath
[New!] 上記以外にも、数学と諸科学・産業の協働に関する情報を入手次第、本SNSサービスを通して発信しております。数学と諸科学・産業の協働に関連する取り組みのSNSサービスによる発信を希望される方は、事務局までお問い合わせください。
2014年8月号(配信:2014年7月25日)
開催案内(8月) ○2014. 7/30 - 7/31 "Workshop on complex systems modeling and estimation challenges in big data" 開催場所:統計数理研究所 運営責任者:松井 知子 http://coop-math.ism.ac.jp/event/2014W01 http://www.ism.ac.jp/events/2014/meeting0728_31.html
○2014. 7/31 - 8/2 「数理腫瘍生物学の確立を目指して」 開催場所:ラフォーレ新大阪 (7/31, 8/2), 新大阪ブリックビル (8/1) 運営責任者:鈴木 貴 http://coop-math.ism.ac.jp/event/2014S02
2014年9月号(配信:2014年8月30日)
開催案内(9月) ○2014. 9/4 「数理科学の物質・材料科学への応用」 開催場所:政策研究大学院大学 想海樓ホール 運営責任者:松江 要 http://coop-math.ism.ac.jp/event/2014W02
○2014. 9/14 - 9/15 「統計科学の新展開と産業界・社会への応用」 開催場所:東京大学本郷キャンパス 教育学部棟 運営責任者:大森 裕浩 ほか http://coop-math.ism.ac.jp/event/2014W03 http://coop-math2014.e.u-tokyo.ac.jp
○2014. 9/17 - 9/18 「量子系の数理と物質制御への展開:量子ウォークを架け橋に」 開催場所:東北大学 情報科学研究科棟 大講義室 運営責任者:瀬川 悦生 ほか http://coop-math.ism.ac.jp/event/2014E01 http://www.dais.is.tohoku.ac.jp/~smart/forum/index.html#QuantumWalk2014
○2014. 9/20 - 9/21 「生命科学・数学・情報科学による新たな理論生命科学へのアプローチ」 開催場所:ラフォーレ蔵王 運営責任者:飯田 渓太 ほか http://coop-math.ism.ac.jp/event/2014W04 http://www.dais.is.tohoku.ac.jp/~smart/forum/index.html#MultidisciplinaryApproachForum2014
○2014. 9/26 「数学連携ワークショップ~様々な世界に広がる数理」 場所:広島大学 第6会場(K211教室) 主催:文部科学省/統計数理研究所:数学協働プログラム 共催:日本数学会 http://mathsoc.jp/meeting/hiroshima14sept/RenkeiWS.html
「変化係数モデルを用いた予測モデルの構築とその応用」 栁原 宏和(広島大学大学院理学研究科)
概要:重回帰モデルは,目的となる変数 (目的変数) の平均構造を複数の他の変数 (説明変数) の線形結合によって記述するモデルであり,目的変数の値を説明変数により予測したいときによく用いられる.重回帰モデルにおいて,線形結合の係数である回帰係数は,対応する説明変数の目的変数への影響度合いを表しており,それらはすべてのデータにおいて一定である. しかしながら実際のデータでは,回帰係数が位置や時間などによって変化していると考えられる場合がある.例えば, 住宅価格を目的変数とし,最寄駅までの距離を説明変数とした場合,一般的には最寄駅から近い住宅の方が価格は高くなると考えられるが,田園調布や芦屋などの高級住宅地と呼ばれる地域ではそのような関係が逆になっている場合が考えられる.そのため,すべての住宅において,同一の係数により影響を表現することには無理があると考える.このような問題は,ダミー変数を多く用意することで回避することもできると考えられるが,どのようなダミー変数をいくら用意すればよいかという問題が残る.その他として,位置や時間によって回帰係数の大きさが変化する重回帰モデルを用いるという解決法がある.このモデルが変化係数モデルである. 本発表では,この変化係数モデルを用いた予測モデルの構築法とその応用例として土地価格に関する解析結果を紹介する.
「数理科学と臨床医学の協働戦略」 水藤 寛(岡山大学大学院環境生命科学研究科)
概要:この講演では、我々のCREST研究チームにおいて数理科学者と臨床医が協働を続けている、あるいは模索している営みを紹介し、双方の分野の様々な違いを乗り換えて意味のある結果に結びつけていくための戦略について述べたい。 臨床医療診断は伝統的に医師の経験を最も重視してきた。近年は、経験の蓄積を統計学的な裏付けの元に体系化するEvidence based medicine ということが言われているが、経験の蓄積が重要であることには変わりがない。そこに数理科学的な見方やモデルを入れるというのは、病態の進行に関するメカニズムを説明する論理を導入し、広く理解が可能な体系とするということである。また、熟練医は卓越した技能を持っているが、それはなかなか後輩に一言で伝えられるものではない。そのような技能を論理化・言語化することができれば、それを後輩に伝えていくことが容易になる。 例として、個人差の大きい大動脈形状の特徴付けと病態の関連付け、及び肝臓癌の診断における熟練医の判断論理の抽出を取り上げる。このような試みは、基本的に経験に基づく臨床医の思考プロセスに新たな判断論理を補充・補強するものであり、それによって臨床医の判断プロセスがより信頼性が高く幅広いものになることことが期待されるのである。
「映像解析によるオブジェクト動作認識と放送への応用」 高橋 正樹(NHK放送技術研究所 ハイブリッド放送システム研究部)
概要:映像中から特定物体(オブジェクト)を検出し,その画像領域を高速かつ頑健に追跡するためには,数学の理論が必要となる.例えばスポーツ映像解析において,選手やボールの領域を追跡する場合,各オブジェクトの移動軌道予測に基づく効率的な処理が求められる.また映像中の人物の動作内容理解など,各種認識処理においても数学の知識が不可欠である.スポーツ中継での例を軸に,数学が番組制作の現場でも活用されていることを示す.
数学会のページには、講演者の先生の経歴も掲載されます。
2014年10月号(配信:2014年9月30日)
開催案内(10月) ○2014. 10/2 「自然言語処理と最適化」 開催場所:九州大学伊都キャンパス 運営責任者:神山 直之 ほか http://coop-math.ism.ac.jp/event/2014E02
○2014. 10/14 - 10/15 「航空機開発における不確実性への統計数理科学の応用」 開催場所:統計数理研究所 運営責任者:加藤 博司 http://coop-math.ism.ac.jp/event/2014S03
○2014. 10/25 「数学・数理科学専攻若手研究者のための異分野・異業種研究交流会」 開催場所:東京大学駒場キャンパス数理科学研究科棟 主催:日本数学会 共催:日本応用数理学会、統計数理研究所「数学協働プログラム」、東京大学数物フロンティア・リーディング大学院 後援:日本経済団体連合会 http://coop-math.ism.ac.jp/event/2014C01 http://mathsoc.jp/administration/career/
○2014. 10/31 - 11/2 「数理医学体験ワークショップ~日仏数学者による秋の学校」 開催場所:大阪大学国際棟(シグマホール、セミナー室) 運営責任者:鈴木 貴 http://coop-math.ism.ac.jp/event/2014W05
2014年11月号(配信:2014年 月 日)開催案内(11月)
○2014. 11/7 - 11/8 「ウェーブレット理論と工学への応用」 開催場所:大阪教育大学 天王寺キャンパス西館2階・第5講義室 運営責任者:守本 晃 ほか http://coop-math.ism.ac.jp/event/2014E05
○2014. 11/9 「数学協働プログラム 講演会・展示 in サイエンスアゴラ2014」 後述。
○2014. 11/12 - 11/14 「デジタル映像表現のための数理的手法」 開催場所:九州大学西新プラザ 運営責任者:落合 啓之 http://coop-math.ism.ac.jp/event/2014E03 http://mcg.imi.kyushu-u.ac.jp/meis2014/
○2014. 11/13 - 11/14 「地球科学における極端現象と疎構造」 開催場所:京都大学数理解析研究所 運営責任者:森 重文 ほか http://coop-math.ism.ac.jp/event/2014S05
○2014. 11月下旬 「数理シミュレーション高度化を通じたリチウムイオン電池の高信頼性実現」 開催場所:統計数理研究所 運営責任者:椿 広計 ほか http://coop-math.ism.ac.jp/event/2014S04
サイエンスアゴラ2014 サイエンスアゴラ2014にて、以下の企画を実施いたします。
1. 講演会「科学における発見、数学における発見」 2014. 11/9 10:00 - 12:00 開催場所:東京国際交流館3階 メディアホール 最先端の科学研究において新しい事実の発見がどのように行われるか、そこに至るまでに研究者が直面する困難や、発見したときの喜びを研究者の皆さまに語っていただきます。特に、数理科学的な手法を多用する研究分野において、数理的手法と発見の関係に焦点を当てます。
総合司会:砂田 利一(明治大学) 「水の中に見つかったミクロなネットワークの意外な役割」 語り手:赤木 和人(東北大学) 聞き手:寺本 紫織(フリーランスディレクター) 「アリの性比はなぜ3:1なのか? - 生物の進化理論と数学 -」 語り手:若野 友一郎(明治大学) 聞き手:横山 広美(東京大学) 「大望遠鏡で迫る宇宙の果て - 古代天体ヒミコの発見を導いた数学 -」 語り手:大内 正己(東京大学) 聞き手:江田 慧子(信州大学)
「パネルディスカッション - 数理を中心に据えた科学の異文化交流 -」 原子レベルのミクロの世界、宇宙空間の大規模構造、そして摩訶不思議な生物の進化など、科学の第一線で活躍する若手の研究者が知の広場「アゴラ」に集まり、数理を中心に据えた科学の異文化交流が今ここから始まります!この交流の中で、科学研究のロマン、どのように発見が成されたか、そして未来の科学に対する夢について思う存分語っていただきます。
2. 展示「『創って動かす』生物研究 - 数理科学とロボット工学からのアプローチ -」 2014. 11/9 10:00 - 17:00 開催場所:日本科学未来館1階 企画展示ゾーン 出展:石黒 章夫、大脇 大、加納 剛史(東北大学)、小林 亮(広島大学)、風間 俊哉(統計数理研究所)
生き物は環境に応じて多種多様に動きます。この動きの仕組みを理解する1つの方法は、生き物を真似たロボットを創り、うまく動くか確かめる事です。本展示では、生物模倣型ロボット「ヘビ型ロボット」「四脚歩行ロボット」「クモヒトデ型ロボット」「ヒラムシ型遊泳ロボット」の展示・実演を行い、生き物の動きを「創って動かす」事により理解する研究を紹介します。ロボットを制御する種々の数理モデルを試す事により、生き物の動きの仕組みが理解されます。数理的手法はこのように生物研究にも役立ちます。数理科学の諸科学への活用促進を目指す文部科学省委託事業「数学協働プログラム」が支援する研究の一例として本展示を行います。
数学協働プログラムのホームページの中に、サイエンスアゴラ特設ページを開設いたしました。 http://coop-math.ism.ac.jp/info/Agora 数学協働プログラムが提供する全てのアゴラ企画情報は、このページにて公開いたします。 9/29現在、広告・ポスター(低解像度版)をこちらでダウンロードできるようになっております。正規版は紙媒体にて、10月1日より配布を開始いたします。
2014年12月号(配信:2014年 月 日)開催案内(12月)
○2014. 12/2 - 12/4 「生命ダイナミクスの数理とその応用:異分野とのさらなる融合」 開催場所:東京大学大学院数理科学研究科、京都大学芝蘭会館(稲盛ホール) 運営責任者:井原 茂男 ほか http://coop-math.ism.ac.jp/event/2014W07 http://www.ibmath.jp/news1/2014W07/entry.html
○2014. 12/3 - 12/5 「高信頼な理論と実装のための定理証明および定理証明器」 開催場所:九州大学西新プラザ 運営責任者:溝口 佳寛 ほか http://coop-math.ism.ac.jp/event/2014E04 http://imi.kyushu-u.ac.jp/lasm/tpp2014/index_ja.html
○2014. 12/3 - 12/5 「機械学習における情報幾何学的視点」 開催場所:理化学研究所 脳科学総合研究センター 運営責任者:池田 思朗 ほか http://coop-math.ism.ac.jp/event/2014W08 https://sites.google.com/site/infogeom2014/
○2014. 12/8 「甚大災害の外力想定に必要となる極値統計解析法の背景と活用」 開催場所:京都大学 防災研究所 宇治おうばくプラザ・きはだホール 運営責任者:北野 利一 ほか http://coop-math.ism.ac.jp/event/2014W09 https://docs.google.com/forms/d/1Foty-QL2pmduaT1pIfyNlWfocP1J20EDOWwhnM5_MQY/viewform?c=0&w=1
○2014. 12/8 - 12/12 「産業・異分野における課題解決のためのスタデイグループ」 開催場所:東京大学大学院数理科学研究科 運営責任者:山本 昌宏 ほか http://coop-math.ism.ac.jp/event/2014S07 当日に提供される課題は以下の通りです。 12月8日(月)10:00-12:00,東京大学大学院数理科学研究科123号室:参加3社からの課題提起と説明 10:00-10:30 ニコン株式会社 「非線形識別器における有効な特徴量選択について」 10:30-11:00 花王株式会社 「タンパク質の3次元の構造同定の簡単なアルゴリズムについて」 11:00-11:30 東和精機株式会社 「全自動歪取機制御ソフトにおける計測アルゴリズムの改良」
○2014. 12/9 - 12/11 「多孔質媒体の移動と内部構造を考慮した流体モデルの構築」 開催場所:明治大学中野キャンパス 運営責任者:池田 幸太 http://coop-math.ism.ac.jp/event/2014S08
○2014. 12/11 - 12/12 「新たなウイルス出現を予測する数理的手法の妥当性検証と比較」 開催場所:統計数理研究所 運営責任者:斎藤 正也 ほか http://coop-math.ism.ac.jp/event/2014S06
○2014. 12/12 「サービス科学を拓く数理モデルとアルゴリズム」 開催場所:大阪大学吹田キャンパス銀杏会館 運営責任者:梅谷 俊治 ほか http://coop-math.ism.ac.jp/event/2014W10
○2014. 12/15 - 12/16 「揺らぎと遅れを含む力学の数理と応用」 開催場所:名古屋大学大学院多元数理科学研究科 運営責任者:大平 徹 ほか http://coop-math.ism.ac.jp/event/2014W06
○2014. 12/26 (開催日が変更になりました) 「健康増進・ヘルスプロモーションに関する数学ニーズの発掘」 開催場所:福井大学文京キャンパス・アカデミーホール 運営責任者:高田 宗樹 http://coop-math.ism.ac.jp/event/2014E06
2015年1月号(配信:2015年 月 日)開催案内(2015年1月)
☆1月開催のワークショップ・スタディグループはありません。
☆サイエンスアゴラ2014にて、数学協働プログラムの出展企画「展示:『創って動かす』生物研究 - 数理科学とロボット工学からのアプローチ」が「サイエンスアゴラ2014 リスーピア賞」を受賞いたしました。 先日、サイエンスアゴラの公式サイトにて詳細が公開されました。こちらも併せてご覧ください。
数学協働プログラム in サイエンスアゴラ2014:http://coop-math.ism.ac.jp/info/Agora サイエンスアゴラ賞ほか:http://www.jst.go.jp/csc/scienceagora/reports/prize/
2015年2月号(配信:2015年 月 日)開催案内(2015年2月)
○2015. 2/6 「数理シミュレーション高度化を通じたリチウムイオン電池の高信頼性実現」 (2回め) 開催場所:統計数理研究所 運営責任者:椿 広計 ほか http://coop-math.ism.ac.jp/event/2014S04
○2015. 2/11 - 2/12 「社会システムデザインのための数理と社会実装へのアプローチ」 開催場所:九州大学マス・フォア・インダストリ研究所 大講義室1 運営責任者:吉良 知文 ほか http://coop-math.ism.ac.jp/event/2014E07 http://imi.kyushu-u.ac.jp/~kira/ws/social.html
○2015. 2/12 - 2/13 「気象データへの幾何・トポロジーによるアプローチの模索」 開催場所:北海道大学大学院理学研究院 運営責任者:稲津 將 http://coop-math.ism.ac.jp/event/2014E08
○2015. 2/16 - 2/20 「産業・異分野における課題解決のためのスタデイグループ」 開催場所:東京大学大学院数理科学研究科 運営責任者:山本 昌宏 ほか http://coop-math.ism.ac.jp/event/2014S07
○2015. 2/19 - 2/21 「Topological Data Analysis on Materials Science」 開催場所:東北大学原子分子材料科学高等研究機構(WPI-AIMR) 運営責任者:平岡 裕章 http://coop-math.ism.ac.jp/event/2014W11
2015年3月号(配信:2015年 月 日)開催案内(2015年3月)
○2015. 3/8 「物理学と統計学の接点:新潮流と展望」 開催場所:明治大学中野キャンパス (第9回日本統計学会春季集会会場) http://www.jss.gr.jp/ja/convention/spring/09/JSSspring2015_program.html 講演1:岡田 真人(東京大学)「レプリカ交換法を用いた変数選択」 講演2:田中 冬彦(大阪大学)「量子統計:実験技術の進歩にともなうニーズの変遷と新たな課題」 講演3:鹿野 豊(分子科学研究所) 「実験家の協働で見えてきた統計的考え方の重要性と期待」 講演4:文部科学省 「文部科学省および数学協働プログラムの活動紹介」
○2015. 3/16 - 3/17 「生命ダイナミクスの数理とその応用:異分野との更なる融合 ー 実践編 生命 動態の分子メカニズムと数理」 開催場所:京都大学芝蘭会館(稲盛ホール) 運営責任者:井原 茂男 ほか http://coop-math.ism.ac.jp/event/2014W12
○2015. 3/19 - 3/20 「確率的グラフィカルモデル」 開催場所:電気通信大学大学院情報システム学研究科 運営責任者:鈴木 譲 http://coop-math.ism.ac.jp/event/2014W13
○2015. 3/23 「数学連携ワークショップ -- 生物学と数理科学の協働 --」 開催場所:明治大学駿河台キャンパス(日本数学会2015 年度年会会場) 講演1:西浦 博 (東京大学大学院医学系研究科)「感染症流行の数理モデル:エボラ出血熱モデリング事例」 講演2:郡 宏 (お茶の水女子大学理学部情報科学科)「時差ボケをめぐる実験と数理の協働」 講演3:間野 修平 (統計数理研究所)「拡散の双対としての系図」 報告:藤澤 洋徳 (統計数理研究所)「数理生命科学作業グループの活動報告」 http://mathsoc.jp/meeting/meiji15mar/
○2015. 3/23 「第4回数学・数理科学のためのキャリアパスセミナー:数学イノベーションを 担う人材育成に向けて」 開催場所:明治大学駿河台キャンパス(日本数学会2015 年度年会会場) 運営責任者:舟木 直久 http://coop-math.ism.ac.jp/event/2014C02
|