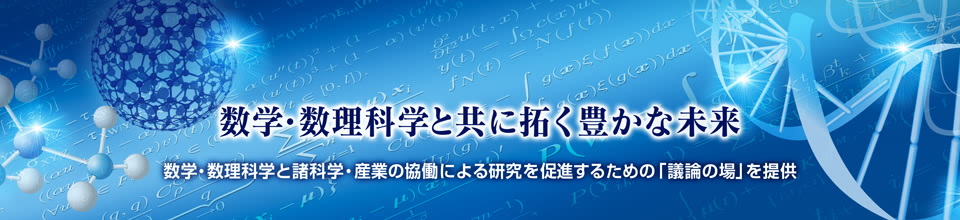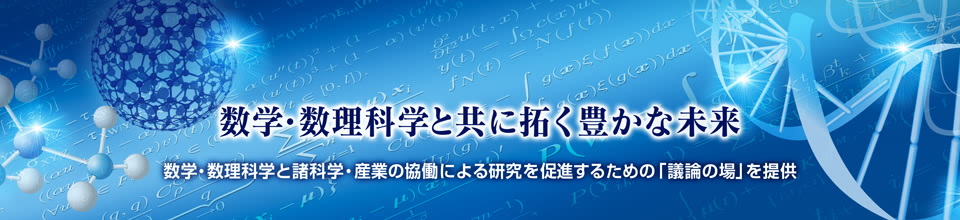ビッグデータ応用の展開と課題:ガンの個別化医療と都市除排雪への応用を事例として
田中 譲:講演資料: 01_田中_数学協働プログラムワークショップ講演資料 01_田中_数学協働プログラムワークショップ講演資料
ビッグデータの持つ本質的な意味を議論し、どのような対応が求められるかについて、一般的考察を加え、講演者が関わってきた関連プロジェクトにおいて、それらがどのように実行されてきたかを説明した。また、それら全体の中で、物質・材料研究における本質的な問題点を議論した。
簡便エミュレーションによる実験計画のスマート化
樋口知之:講演資料: 02 MI2I数協160226_樋口 02 MI2I数協160226_樋口
まず、シミュレーションに含まれる本質的な不定性と誤差の集積を補正するために用いられるデータ同化の概念を説明し、欧米で進められている Uncertainty Quantification を紹介した。また、原理による予測が困難な現象を模倣するエミュレーションの概念と、その方法論を説明した。
Natural processes and scientific reasoning
Rene Vestergaard:講演資料: 03 vestergaard 03 vestergaard
形式理論(数理論理学)を自然科学の問題に適用した一例として、λファージの遺伝子スイッチの問題を扱った研究の紹介をした。具体的には、Mark Ptashne 著 ”A Genetic Switch” の内容を、形式理論に翻訳した。それによって、多くの記述の間の論理的な整合性が検証されるだけでなく、種々の条件の組み合わせの結果の予測が可能になる。
製造プロセスにおける数理的研究の現状と、数理科学と物質・材料の連携の展開について
中川淳一:講演資料: 04_講演資料(2016.2.26新日鐵住金・中川)_公開用 04_講演資料(2016.2.26新日鐵住金・中川)_公開用
要旨: 04A_講演要旨[新日鐵住金・中川] 04A_講演要旨[新日鐵住金・中川]
大規模数値シミュレーションによるものづくりの革新 ~京の成果と今後の展開~
加藤千幸:講演資料: 05_大規模数値シミュレーションが実現する技術革新(加藤)_公開用 05_大規模数値シミュレーションが実現する技術革新(加藤)_公開用
大規模数値シミュレーションの例として、流体力学計算の先端的研究の紹介をした。産業での活用の観点からは、さまざまな試作試験の完全な代替を目指す、という視点での取り組みが行われた。例えば、車両内部の音響解析や、曳航水槽試験の代替などでの成功例がある。
数学・材料科学連携による構造・機能・プロセスの理解への挑戦
小谷元子:講演資料非公開
数学と他分野との連携促進が進められており、東北大学の原子分子材料科学高等研究機構(http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/index.html)では、物質・材料科学との共同研究が多面的に行われ多くの成果が得られている。数学と物質・材料科学の連携の意義、可能性を説明し、具体的な活動例を紹介した。要旨: 06_要旨_小谷 06_要旨_小谷
数値解析学から見た計算手法の高精度化・高効率化の取組み、および物質・材料との連携へ向けた展開
田上大助:講演資料: 07_講演資料_田上 07_講演資料_田上
自然現象をシミュレーションする手順は、まず自然現象をモデル化して、数理モデルを作り、それを離散化して近似方程式として数値シミュレーションを実行する。このモデル化と離散化の段階において誤差が生じる。誤差をできるだけ小さくし、計算不可を小さくするための基本的な数学的取り組みを、流体力学と磁場問題を例として説明した。
マテリアルズ・インフォマティクス:分野の特色と課題
Dam Hieu Chi:講演資料: Dam、公開用 Dam、公開用
田中譲教授による最初の講演で議論された、物質・材料科学におけるインフォマティクスの問題点を、より具体的に議論した。バイオ・インフォマティクスや自然言語処理に比較して、マテリアルズ・インフォマティクスの特徴は、記述子の選択が困難であることと、計算機シミュレーションによるデータ生成が容易である、という2点にある。後者は利点であるが、前者の記述子の選択と作成は、マテリアルズ・インフォマティクスの成功の鍵を握るものであり、記述子が満たすべき必要条件、および記述子の望ましい性質を具体的に説明した。要旨: 08_要旨_Dam 08_要旨_Dam
人工知能技術の発展と最近の動向
麻生英樹:講演資料: 09_160226人工知能技術の動向_数学協働WS送付版R2 09_160226人工知能技術の動向_数学協働WS送付版R2
最近のアルファ碁の活躍は、人工知能に対する社会的関心を一層盛り上げた。どのような技術的ブレークスルーによって、アルファ碁が予想をはるかに上回る速度で進化したかを説明した。人工知能の進展には2つの流れがあり、一つは知識駆動型で、他方はデータ駆動型である。IBM Watson は少なくとも質問応答システムとしては前者に属し、最近の画像処理などで用いられる Deep Learningは後者に属する。人工知能の材料科学への応用についても説明した。
材料科学分野の数理との連携に関わる動向および潜在的可能性
松江 要:講演資料: 10 20160226_松江(材料科学分野の数理連携) 10 20160226_松江(材料科学分野の数理連携)
数学・数理科学と物質・材料科学の協働のこれまでの経過、現状、課題を紹介した。関連の活動は各地で行われているが、実りに結びつけるにはいろいろの困難がある。カルチャーの違い、言葉の違い、狙いの共有化の困難、などである。数学者である講演者の立場から、数学協働を促進し、実りを挙げるために必要なものについて提言した。 |