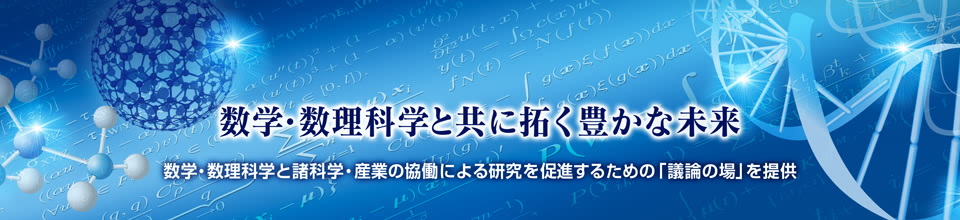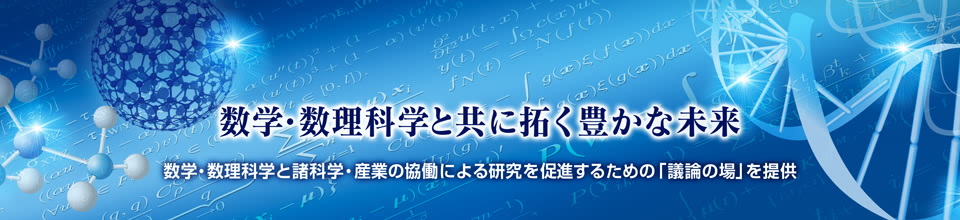東京国際交流館 3階メディアホール
2014年11月9日 10:00 ~ 12:00
総合司会 砂田利一(明治大学総合数理学部長)

講演1. 水の中に見つかったミクロなネットワークの意外な役割
赤木和人(東北大学WPI-AIMR) 聞き手: 寺本紫織(フリーランスディレクター)
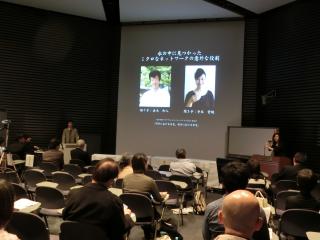 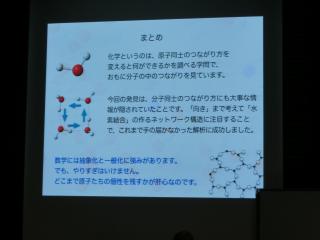
講演2. アリの性比はなぜ3:1なのか? - 生物の進化理論と数学
若野友一郎(明治大学総合数理学部) 聞き手: 横山広美(東京大学理学部)
 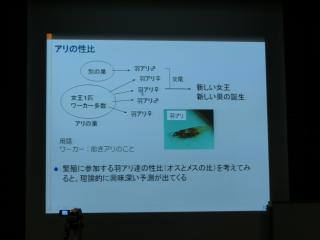
講演3. 望遠鏡で迫る宇宙の果て - 古代天体ヒミコの発見を導いた数学
大内正己(東京宇宙線研究所) 聞き手: 江田慧子(信州大学山岳科学研究所)
 
パネルディスカッション - 数理を中心に据えた科学の異文化交流
 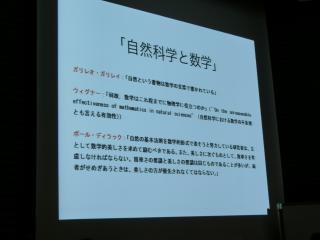
ロボット展示 - 『創って動かす』生物研究
日本科学未来館1階企画展示ゾーン
2014年11月9日 10:00 ~ 17:00
(東北大学 石黒章夫研究室、広島大学 小林亮研究室の協力による)
ヘビ型ロボット
四脚歩行ロボット
クモヒトデ型ロボット
ヒラムシ型遊泳ロボット
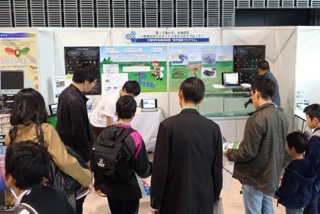
四脚歩行ロボット(東北大学石黒章夫研究室提供)はリスーピア賞を受賞した
 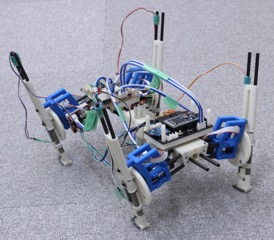
 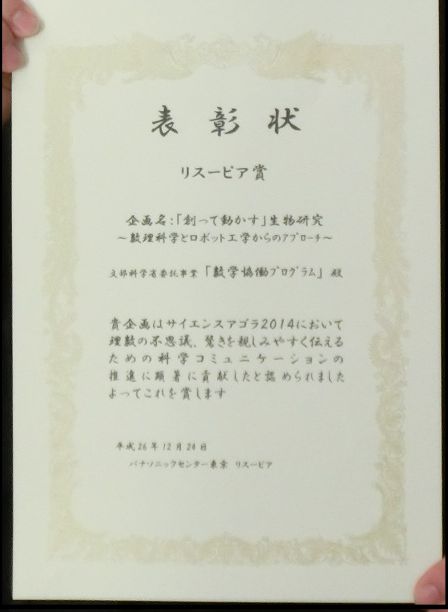
2014年12月24日に行われたリスーピア賞授賞式
|