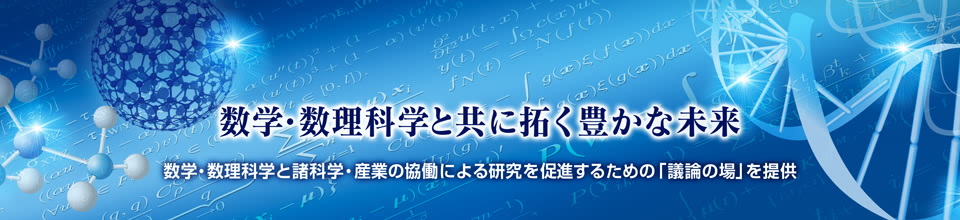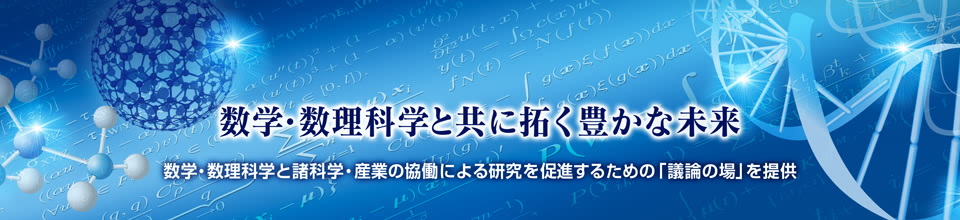以下、各講演の要旨を記載する。
概要や講師の略歴については、
http://mathsoc.jp/administration/career/4th_career_abstract.pdf
を参照されたい。
講演1:数学イノベーション戦略と人材育成
文部科学省「数学イノベーション委員会」主査 九州大学 理事・副学長
若山 正人氏
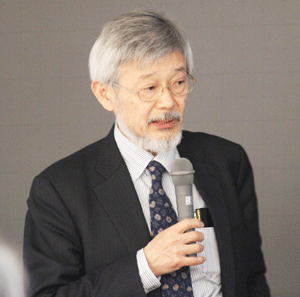
【講演要旨】
1.数学イノベーション委員会の設立背景
a) 2006年に文部科学省・科学技術・学術政策研究所よりNISTEP REPORT 2006「忘れられた科学 – 数学」が発刊された。この報告書を通して、基礎学問としての数学振興並びに数学応用分野の振興・推進、産業界を含めた数学研究人材育成が大きな課題であることが明らかとなった。
b) 2008年に、OECD/Global Science Forum から、”Mathematics in Industry” なる報告書が発刊された。この報告書では、NISTEP REPORT 2006と同様に、研究活動と人材育成の重要性が提言された。
c) 2011年に、世界的潮流に乗り遅れつつある、日本での数学の応用研究や人材育成に関する課題解決のため、文部科学省科学技術・学術審議会の下に「数学イノベーション委員会」が設置された。
2.数学イノベーション戦略
「数学イノベーション委員会」での検討内容は、2014年8月に「数学イノベーション戦略」として取りまとめられた。主な項目は次の通りである。
a) 数学イノベーションが必要とされる背景
b) 数学イノベーションの推進方策
数学へのニーズの発掘から数学と諸科学・産業との協働へつなげる活動/数学研究者と諸科学・産業との協働による研究の推進/数学イノベーションに必要な人材の育成/情報の発信
c) 数学イノベーション推進に必要な体制
d) 数学イノベーション推進により目指す将来の姿
【注】詳細については、文部科学省「数学イノベーション戦略について」
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu23/002/houkoku/1352402.htm
を参照されたい。
3.数学イノベーションに必要な人材の育成の成功事例
九州大学では、2006年に博士課程学生を対象とした長期の研究インターンシップを開始した。今まで50名余りの参加がある。なお、博士号取得後、企業の研究・開発部門以外にも、大学や公的研究所に就職したものも少なくない。
4.米国労働統計データの紹介
2014年1月に公開された米国労働統計データ(2012年度末情報)によると、米国における数学人材の活躍の場が大きく広がっている。
講演2:企業における数学人材の活躍と数学人材育成への取り組み
日本電気株式会社 情報・ナレッジ研究所 エグゼクティブエキスパート
福島 俊一氏
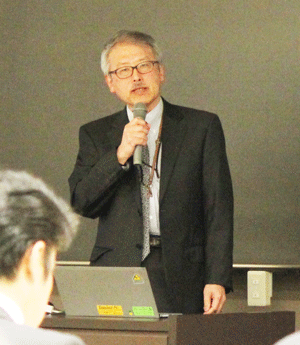
【講演要旨】
1.大規模複雑化する社会システムと数理的アプローチ
情報通信技術が社会を支える一方、社会システムのボーダーレス化・大規模複雑化が進展した。このような大規模・複雑化した課題の解決には、実世界の膨大なデータすなわちビッグデータから規則性を抽出して、それを数理モデル化し、数理モデルから意思決定・アクション等の解決策を導き出すアプローチが有効である。
2.ビッグデータを使った数理的アプローチの成功事例
a) 異常の予兆検出
水道網の漏水や道路網の亀裂等に見られる、人間の感覚では察知できない微小な予兆を検出することに成功した。特に、膨大なセンサーデータ間の相関関係をインバリアントに着目した数理モデルがこの検出に貢献した。
b) 安全・安心な生活
不審者の認識・追跡や真贋判定等の人間の感覚では見えない/見分けられない特徴を捉えて犯罪や偽装を防止し、安全・安心な生活を実現することに成功した。顔認証においては、NEC独自の機械学習技術と特徴量選別により対象・環境に変動に対する頑健性を保証する技術を確立した。
c) 将来の需要予測
様々な要因が複雑に絡み合った現象から規則性をモデル化することにより、電力等のエネルギーの需要予測に成功した。この実現にあたっては、因子化漸近ベイズ推論を使った異種混合学習が貢献した。
d)データ保護・活用の両立
データベースの内容を暗号化したまま検索・演算可能なシステムの開発に成功した。このアルゴリズムの開発にあたっては、暗号の基盤となる数学である整数論等が貢献した。
3.数学・数理科学人材の活躍への期待と人材育成の取り組み
課題の定式化や分析対象となる振る舞いのモデル化がブレークスルーをもたらし前述したような社会的課題解決に成功した。このブレークスルーにあたっては数学・数理科学の人材の活躍が貢献した。
NEC社では、理論・原理研究にとどまらずシステム実装を通して社会や顧客の価値創造へと結実させる能力を有する人材育成を積極的に行っている。研究者には、近視眼的な課題解決ではなく、社会や顧客へ大きな価値をもたらす大粒の課題を見出す能力を期待する。
4.NEC中央研究所での研究インターンシップ
企業における研究開発のスタイルを学ぶ機会として、1.5ヶ月から6ヶ月のインターンシップを学生に実施している。幅広い情報通信技術分野での多数のテーマ(約70テーマ)を用意しているので、数学・数理科学の学生も積極的に応募して欲しい。
講演3:学会活動を通した数学イノベーションを担う人材育成に向けて-「若手研究者のための異分野・異業種研究交流会」の今後の展開-
早稲田大学理工学術院客員教授 東京大学数理キャリア支援室キャリアアドバイザー
池川 隆司氏
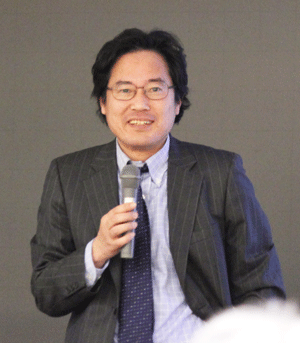
【講演要旨】
1.若手数学者を取り巻く環境の変化
情報通信技術等の進展に伴い、高度な数学・数理科学の知識を必要とする研究者・技術者の需要が増している。2014年の米国での職業評価結果の報告によると、数学者 (Mathmatician)がベストジョブとなった(同じ内容が、若山氏の講演においても報告されている)。
2.日本数学会におけるキャリア構築支援活動の振り返り
「将来を担う若手数学研究者の育成」は、日本数学会として重要な事業の一つである。その事業の一環として、「数学・数理科学のためのキャリアパ スセミナー」を 2012 年から数学会年会時に開催してきた。本セミナーは多くの学会員が参加する盛況なセミナーとなっている。昨年は本セミナーに加え、次に述べる「異分野・異業種研究交流会」を開催した。
3.「異分野・異業種研究交流会」とは
若手数学研究者に、1) 数学の思わぬ力(「産」への応用展開の可能性等)の発見、2)「産」へのキャリアパス構築に向けた動機付けを与えるために、「産」と「学」間の双方向の交流を実現する研究交流会を、2014年10月に東京大学にて開催した。
産官学から約130名に及ぶ多数の参加者があり、盛況に終えることができた。今回、「若手研究者によるポスター発表」の場を設けたところ、博士課程の履修生を中心とした37件の発表があった。ポスター発表に対する企業関係者のアンケート結果によると、「熱意を感じた」、「説得力があった」等の好意的感想をもらった。
4.今後の展開
高度な数学・数理科学の知識のみならずTransferableスキルを有する数学人材を、産官学協働によって育成する「数学人材育成エコシステム」の構築が必要である。今後は、その構築に向けた活動を実践したい。
「異分野・異業種研究交流会2015」を2015年11月に東京大学にて開催するので多数の参加をお待ちしている。
【講演資料】
http://faculty.ms.u-tokyo.ac.jp/users/career/pdf/career_seminor2015.pdf
【配布資料】
池川 隆司: "「数学・数理科学専攻若手研究者のための異分野・異業種研究交流会」開催報告-若手数学者の研究のさらなる拡がりとキャリア開発に向けて-", 日本数学会数学通信, Vol.19, No. 4, pp. 26 - 33, 2015年2月 (招待論文).
http://mathsoc.jp/publication/tushin/1904/career2014.pdf |