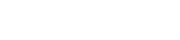AI個別最適化スマートフォン認知行動療法を開発 ―治療効果35%向上:大規模臨床試験で有効性を確認―
ISM2025-06
2025年8月20日
【概要】
古川壽亮 京都大学成長戦略本部特定教授、野間久史 統計数理研究所教授、田近亜蘭 医学研究科健康増進・行動学分野准教授、豊本莉恵 同特定助教らの研究グループは、日本で行われた世界最大規模のスマートフォン認知行動療法(CBT)試験(RESiLIENT試験、4,469人参加)のデータに基づき、どういう人にどの認知行動スキルが有効かをAIにより解析し、個人ごとに最適な治療を推奨し介入効果を高める「個別最適化治療(POT)アルゴリズム」を開発しました。
POTアルゴリズムは、ベースライン情報や早期の治療反応から26週時点での抑うつ症状の改善を予測し、各参加者に最適なCBTスキルまたはその組み合わせを推奨します。シミュレーションでは、POTによる介入は、対照群と比較して抑うつスコアを−1.41点改善させました。これは、グループ平均で最も効果的だった治療と比較して35%効果が高く、特にグループ平均ではベストとされた治療が最適ではない人々ではその人にマッチした個別最適化介入を受けることで64%の効果増が得られました。
このPOTアルゴリズムはスマートフォンアプリへの実装が可能で、個人の強みや弱みを特定することで推奨理由を説明できるため、臨床的価値が期待されます。ただし、その効果を確認するためには、独立した新たなランダム化臨床試験が不可欠です。
本研究成果は、2025年8月20日に国際学術誌「npj Digital Medicine」にオンライン掲載されました。
|
|
| 図1:うつ症状の26週間の推移。様々なスマートフォン認知行動介入(カラフルな実践)により、対照群(灰色)よりも26週間にわたってうつ症状が軽減するが、個別最適化介入群(黄金色)はそれらよりもさらにうつ症状が軽減する。 |
【背景】
うつ病は連続的なスペクトラムとして存在し、診断基準を満たさない「閾値下うつ状態」(subthreshold depression)も一般的に見られます。このように病気のレベルに達しない抑うつ状態は、社会機能の障害、生活の質の低下、医療サービス利用の増加、死亡率の上昇と関連しており、個人の負担は重症うつ病ほどではないものの、その高い有病率から社会全体の経済的コストは同規模に達するとされています。さらに、閾値下うつ状態を経験する個人は、大うつ病エピソードへ進行するリスクが3倍も高いことが指摘されています。
精神療法はうつ病の全スペクトラムにわたって効果的であり、現在のガイドラインでは、閾値下から軽度の大うつ病に対して精神療法を一様に推奨しています。しかし、メタアナリシスによれば、精神療法を受けた参加者の約半数がフォローアップ期間中も症状が残存する可能性があり、治療法の改善が喫緊の課題となっています。
この改善に向けた有望なアプローチの一つが、個々の患者の特性に合わせて様々な精神療法を最適化し、個人レベルおよび集団全体の有効性を高めることです。これは、治療効果を左右する予後因子と効果修飾因子の特定に基づいた、いわゆる「精密医療」への高い期待とニーズがあることを意味します。これまでの精神療法の精密医療の研究は、単一の介入と非治療対照の比較に留まることが多く、複数の治療選択肢の中から個々人に最適な治療を推奨し、それが集団全体のアウトカムを改善するかどうかという、公衆衛生上より重要な問いには答えられていませんでした。
【研究手法・成果】
わたしたちの研究グループは、このような背景のもと、個人の特性に合わせて最適な精神療法を推奨する「個別最適化介入(POT)アルゴリズム」を開発しました。このアルゴリズムは、日本で実施された大規模なスマートフォン認知行動療法(CBT)無作為化比較試験(RESiLIENT試験)のデータを用いて、AIにより構築されました。RESiLIENT試験には4,469人の成人が参加し、行動活性化、認知再構成、問題解決、アサーショントレーニング、睡眠行動療法という5つのCBTスキルまたはその組み合わせ、あるいは対照群のいずれかを6週間にわたって受けました。全ての介入が対照群に比して有効であることが確認されています。
|
|
POTアルゴリズムは、ベースライン情報と早期の治療反応を用いて、26週目時点での抑うつ症状(PHQ-9スコア)の変化を予測し、各参加者に最適なCBTを推奨します。例えば、PHQ-9スコアが4点以下の参加者にはそれぞれの特徴に応じてアサーショントレーニングまたは不眠行動療法を実施することが最適で、一方5点以上の参加者には行動活性化+認知再構成、行動活性化+問題解決、あるいは行動活性化+アサーションの効果が大きいことが分かりました。特にグループ平均でベストの治療法がその個人に最適ではないと判断された人々に限定した場合、個別最適化介入による介入効果はグループ平均でベストの介入と比較して64%の増加が見られました。
【波及効果、今後の予定】
本研究で開発されたPOTアルゴリズムは、多くの治療選択肢の中から個人ごとに最適な治療法を推奨する、初の精密医療アルゴリズムであり、独立した無作為化試験で効果が確認されれば臨床的に極めて価値があると考えられています。スマートフォンアプリ内での実装も可能であり、アプリは個人の強みや弱みを特定することで、なぜ特定のスキルが選択されたのかを説明できるため、患者の理解と治療へのコミットメントを促進する可能性を秘めています。
しかし、その実用化にはいくつかの課題と今後の研究が必要です。現在の最適化は介入の非常に初期段階(2週目まで)のみを対象としており、参加者が治療経過から外れた場合や、反応しない場合、または再発のリスクがある場合などに対応するための縦断的な最適化が必要と考えられます。また、RESiLIENT試験には、中等度から重度のうつ病症状がある参加者、特に自殺念慮のある参加者は含まれていませんでした。これらの人々に対するPOTアルゴリズムを確立するための新たな研究が求められています。
【研究プロジェクトについて】
本研究は⽇本医療研究開発機構(AMED)「予防・健康づくりの社会実装に向けた研究開発基盤整備事業」の⽀援を受けて実施されました。
【用語説明】
- 閾値下うつ状態(Subthreshold depression):臨床的にはうつ病と診断されないが、抑うつ気分や意欲低下などが継続している状態。
- CBT(Cognitive Behavioral Therapy):認知⾏動療法。思考や⾏動に働きかけることで⼼理的困難の軽減を⽬指す介⼊⽅法。
- 精密医療:その人の遺伝子情報や生活習慣、体の特徴などを調べて、「この人にはこの治療法が合っている」といったふうに、その人にぴったりの治療を選ぶ医療。
- ⾏動活性化(Behavioral Activation):抑うつ気分のときに避けがちな活動をあえて⾏うことで、気分や⾏動を改善する技法。⽇常の楽しみや達成感のある活動を増やすことを通じて、意欲の回復を促す。
- 認知再構成(Cognitive Restructuring):⾃動的に浮かぶ否定的な考え⽅に気づき、より柔軟で現実的な考え⽅に置き換える技法。思考のクセを⾒直すことで感情的苦痛を緩和する。
- 問題解決(Problem Solving):抱えている困難や課題に対して、問題の明確化・⽬標設定・解決策の洗い出し・実⾏計画などのステップを踏んで取り組む技法。実⾏可能な⾏動を通じて現実的対処⼒を⾼める。
- アサーション(Assertiveness):⾃分の気持ちや意⾒を相⼿を尊重しながら適切に表現する対⼈スキル。⾃⼰主張が苦⼿な⼈にとっては、対⼈関係のストレスを軽減する⼿段となる。
- 睡眠⾏動療法(Behavior Therapy for Insomnia):不眠を改善するために、就寝・起床時間の安定化、刺激制御、睡眠制限法などを含む科学的根拠に基づいた⾏動技法。
- 効果サイズ:治療群が、無治療群に⽐してどれくらい効果があるかを標準化した数字で⽰す。0.2 が⼩さな効果、0.5 が中等度の効果、0.8 が⼤きな効果と⾔われる。抗うつ薬のプラセボと⽐較した効果サイズは約0.31 である。
【研究者のコメント】
認知行動療法家として患者さんを診ている間、どの患者さんにどの認知行動療法スキルを学んでいただくのか、経験による処方しかできないことで、ずっと内心忸怩たる思いをしてきました。今回5000人近い人に、5つの認知行動スキルを使ったスマートフォン認知行動療法アプリを使用していただくランダム化臨床試験を行うことにより、はじめてそれぞれのスキルの効果を解明できただけでなく、さらにどの様な人にはどのスキルが向いているかを明らかにすることができました。異なる精神療法を一人一人の特徴にあわせて提供する精密医療を、エビデンスに基づき提供する世界ではじめての仕組みを準備できたと自負しています。これを実際のスマートフォン認知行動療法アプリ「レジトレ!」Version 3.0に実装し、より多くの方に使っていただき、御自身のレジリエンスとメンタルウェルビーイングを高めていただけるサービスをできるだけ早く実現したいと考えています。
【論文情報】
タイトル:Personalised & optimised therapy (POT) algorithm using five cognitive and behavioural skills for subthreshold depression (閾値下うつ病に対する5つの認知行動療法スキルを使った個別最適化介入アルゴリズム)
著者:古川壽亮*, 野間久史*, ⽥近亜蘭, 豊本莉恵, 坂⽥昌嗣, LUO Yan, 堀越勝, 明智⿓男, 川上憲⼈, 中⼭健夫, 近藤尚⼰, 福間真悟, James M. S. Wason, Ronald C. Kessler, Wolfgang Lutz, Pim Cuijpers (*責任著者)
掲載誌:npj Digital Medicine
DOI:10.1038/s41746-025-01906-6
| 本件に関するお問い合わせ先 |
|
統計数理研究所 運営企画本部 企画室URAステーション TEL:050-5533-8580 E-mail:ask-ura@ml1.ism.ac.jp 〒190-8562 東京都立川市緑町10-3 |
プレスリリースpdf版はこちら