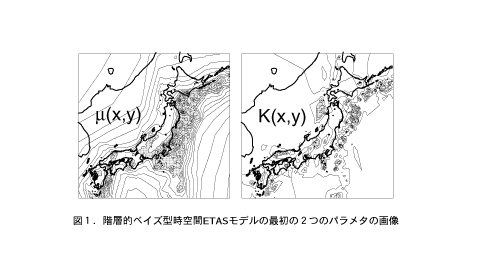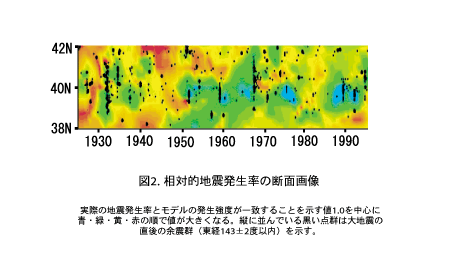−時空間点過程モデルで何ができるのか−
点過程
点過程はある時点時点で突然に起こる現象(点事象)の数学的モデルである。これが地震発生の形態(地震活動)の研究に有効になりえたのには1980年代頃から発展した「条件つき強度関数」という基本概念の存在が大きい。これは、ある時間ある場所での点事象の発生し易さ(発生強度)を、点事象の発生履歴などに基づいて予測するために定義された確率的概念である。最尤法やベイズ法などの統計的方法の進展に伴って地震活動の解析に広い可能性を示しつつある。
大地震の前兆現象を見つける難しさ
地震予知といえば、地震活動の「空白域」や「静穏化」が依然として有効な前兆現象として研究されている。これらは普通、震源分布上の空白や地震発生頻度の時間的な変化として示される。しかし、限られた顕著な場合を別にすれば、目視によるこれらの認定は客観性に乏しい。米国などでは定常ポアソン過程に基づく検定方法が良く使われているが、この方法は余震など群れになって起こる地震の影響を取り除く事に主眼を置くもので、余震除去によるデータ数の減少や除群データの歪みなどについて問題を残している。
階層的ベイズ型時空間モデル
地震の通常の群れ方の癖をモデル化し、その起こり方(発生強度の変化)と実際の地震発生を比較すれば、その異常変化を敏感に検出する事ができる。「ETAS モデル」は、各地震の後にそのマグニチュードに見合った数の余震を伴うというモデルである。そして、ある地域全体での地震の発生強度は、過去に発生した各地震後に減衰する余震強度を重ね合わせたものに、その地域の常時活動の強度を足し合わせたものと考える。我が国においては大森房吉の研究以来、宇津徳冶らを中心として余震発生の時間的減衰や空間的広がりに関する研究が盛んで、それらの経験則はETASモデルやその時空間モデルへの拡張の際の基礎になっている。
最近これを更に拡張して、いわゆる地震(余震)活動の個性(顔)ともいうべき、地域的な違いを表現するベイズ型モデルが開発された。これは特徴を示すパラメタが場所によって異なった値をとるものとし、その値で地震発生様式の地域性が可視化される。例えば図1の等高線図は各位置![]() での常時活動強度
での常時活動強度![]() と、本震の大きさに対して基準化された余震活動の初期強度
と、本震の大きさに対して基準化された余震活動の初期強度![]() を示している。この他に、余震の時間的減衰係数
を示している。この他に、余震の時間的減衰係数![]() など、余震群の時間及び空間的特性を示す3つのパラメタの図があるが割愛した。ここで、これらのパラメタは時間変化t
に関しては無関係としたが、これは以下に説明する様な異常活動の検出に必要なことである。
など、余震群の時間及び空間的特性を示す3つのパラメタの図があるが割愛した。ここで、これらのパラメタは時間変化t
に関しては無関係としたが、これは以下に説明する様な異常活動の検出に必要なことである。
どうやって空白や静穏化を見つけるか
「相対的地震発生率」と呼ばれるものは、各時間・場所における、前述のモデルの地震発生強度に対する実際の地震発生率の割合である。この量の時空間(時間、経度、緯度)上での変化を多数のパラメタで表現し、ベイズ的平滑化法によって推定した。これを3次元画像とすることで、地震活動度の長期トレンドや異常活動が客観的に可視化できる。例えば東経143度で横切った緯度と時間の平面領域上での相対的地震発生率の画像(図2)には青森県沖、三陸沖、宮城県沖における大地震発生の前に相対的な静穏化を示す窪み(寒色系)が明瞭に見られる。
なぜ静穏化するのか
余震活動が静穏化すると隣接部に新たな断層破壊を伴う大きな余震が起きる可能性が高い。更に静穏化が長期間に及ぶと、日本においては、余震域近傍(例えば200km以内)では6年以内に本震と同規模以上の地震が起きる発生確率が通常より数倍以上高い。このような前兆的静穏化現象の仕組みとして次の様な仮説が考えられる。すなわち、来るべき大余震または大地震の断層内の一部または隣接部において、ゆっくりとした前駆的な滑りがあり、それに伴い周辺部で応力が変化しため余震活動がその減衰法則より更に低下したと考えた。実際、発震機構に基づいて計算したクーロンの破壊応力が低下した領域と余震活動が相対的に静穏化した領域の対応が付けられる場合が何例も見られたからである。
何れにしても、相対的地震発生率の変化を解析することによって、地殻内の微弱な応力変化との量的な関係の解明に有望な道が切り開かれると考えている。
(文責 尾形良彦)
尾形良彦 トップページ に戻る
English Page に戻る
統数研のページ
に戻る
Updated on