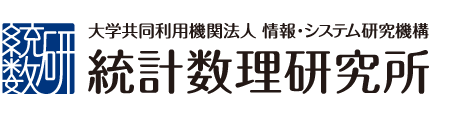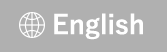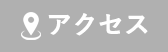公募型人材育成事業
2023年度活動紹介
2023-思考院-7001 『データ同化夏の学校』
※詳細は2023年度統計数理研究所夏期大学院のページをご覧ください。
2023-思考院-7002 『ネットワーク科学研究会』

公募型人材育成事業の助成により2023年12月23〜24日の2日間、同志社大学今出川キャンパス至誠館においてネットワーク科学研究会2023を開催いたしました。 今年度の研究会は現地での対面開催に加え、口頭講演のオンライン配信を行いました。本研究会は「ネットワーク科学」をキーワードに研究を行っている若手研究者を中心に、分野横断的に議論することで相互理解を深めること、情報共有の場を提供することを目的として企画されています。 オンライン参加も含めて110名を超える参加登録があり、80名を超える現地参加がありました。また、5件の全体講演、3件の大学院生による講演、45件のポスター講演がありました。 感染症モデルと接触パターンネットワーク解析や生化学反応ネットワーク解析、さらに金融市場の取引データ解析など様々なトピックの講演があり、分野の垣根を超えた活発な議論が行われました。ネットワーク科学分野と関連する分野の大学院生・若手研究者の交流を深める貴重な機会となりました。
2023-思考院-7003 『理数系教員統計・データサイエンス授業力向上研修集会』

統計思考院公募型人材育成事業として、「理数系教員統計・データサイエンス授業力向上研修集会(宮城)」を「AI/デジタル社会を担う人材育成と教育体系~新課程における統計・データサイエンス教育の実践と高大社接続・産学連携授業~」を全体テーマに、宮城県教育委員会の後援を得て、東北大学データ駆動科学・AI教育研究センターおよびJDSSP 高等学校データサイエンス教育研究会等との共催で、2024年3月23日・24日の2日間にわたって、東北大学川内北キャンパス講義棟において開催した。 当日は2日間で、産官学の関係者延べ260名が参加し、初等中等教育から高等教育・企業における社会人教育に至る統計・データサイエンス人材育成に関連して、学習指導要領の改訂と大学における数理・データサイエンス・AI教育モデルカリキュラムへの接続、とくに、近年注目される生成AIの授業活用について、 16件の講演と活発な質疑が行われた本ワークショップは、データサイエンス系人材としてビッグデータを利活用する学問分野と情報科学技術・統計数理科学分野の両分野に関する知識を持ち,多様な融合領域で能力を発揮できる人材を育成するため、初中等教育から高等教育に至る統計・データサイエンス教育体系化の枠組みおよび職業教育への接続のあり方を調査研究し、現状と課題・将来方向に向けた情報共有を国内外の関連する教育推進組織と連携して行い、理数系関連の教員の授業力向上を図ることを目的に開催するもので、 本年度は、AI/デジタル社会を担う人材育成と教育体系~新課程における統計・データサイエンス教育の円滑実施と高大社接続・産学連携授業~を共通テーマとして、ワークショップを兵庫県と宮崎県で開催した。
2023-思考院-7004 『探索的ビッグデータ解析と再現可能研究』
統計数理研究所統計思考院2023年度公募型人材育成事業(ワークショップ)に採択された 「探索的ビッグデータ解析と再現可能研究」を2023年8月27日(日)にオンラインで開催し、176名の参加者を得た。このワークショップは、ビッグデータ解析の「事例の積み重ねと共有」をテーマとし、解析事例を取り上げ、具体的にデータを処理・解析する工程を、再現可能性も踏まえて詳細に提示することで、 ビッグデータ解析に取り組む人材の育成に資することを目的として開催されました。
2023-思考院-7005 『統計サマーセミナー2023』
統計サマーセミナー2023は2023年8月7日から8月9日まで,福井県あわら市の清風荘で行われた.本セミナーの目的は,研究発表の場を通じて将来の統計科学の発展を担う学生・研究者,あるいは実社会で企業人として統計科学を使いこなせるような人材を育成することにある. 特に本セミナーで重要とすることは,研究発表・討論を通じた若手同士の交流である.多くの研究者・学生が,何らかの個別科学の学部学科等に所属しながら統計科学周辺の研究をしている現在の環境下において, 研究早期の段階からいろいろな個別科学での統計の使われ方に触れ,視野を広げることは極めて重要であり,そのひとつの機会を与えるのがこのセミナーである. 本セミナーでは、65名の研究者・学生,社会人がオフラインで参加した.これにより,視野を広げるための十分多様な研究紹介が可能となり, 活発な議論・討論をすることもできた.これにはこのセミナーならではの理由がある.まず,皆の年齢が近いため,遠慮のない質問・討論が行われることが挙げられる.また 2 回の招待講演を設け,特に学会講演では聴く機会の少ない研究初期段階での問題点やこれまでの研究過程の紹介なども講演者に紹介していただいた.毎晩のセッション終了後は,遅くまで激しく積極的な議論が繰り広げられ,各自が疑問点や様々な主張を繰り広げ, 統計各分野間での活発な交流ができたといえる.すべての参加者にとって,実質的に得るところが大きいセミナーとなった.
2023-思考院-7006 『生物多様性と群集動態:定量化の数理と統計的推定法』
地球規模の環境問題のひとつに生物多様性の消失や減少がある。「消失や減少」を論じるには生物多様性を数値で定量化する必要がある。 生物多様性の定量化は、食う・食われるという食物網と、森林樹木や草原の草食動物など同じ栄養段階の群集レベルに分かれる。それぞれに数理と統計的推定法がある。さらに、種内の遺伝的多様性、種間の生態機能多様性、複数の群集をカバーするランドスケープレベルの多様性などもあり、 それぞれで定量化研究が進められている。生物多様性を志す若手研究者は、野外調査や対象種に関する知識・考察力に加え、定量化についても知識とスキルが必要である。しかし、上記のような広範な中から自身の研究対象に適した定量化法や統計的推定法を選ぶのは、もはや至難の業となっている。 そこで、2023年11月8-10日、長野県菅平高原にある筑波大学山岳科学センターに近い宿泊施設ゾンタックにて、合宿形式で本ワークショップを開催した。45名の参加者のうち26名が大学院生だった。広範な広がりを見せる生物多様性の定量的研究を概観することが若手育成の最初のステップと考え、 解説的講演では質疑を活発に挟みながら聞くことを重視した。また、「野外調査-統計-数理モデル、三位一体の学習」という、統数研に根付く現場主義統計の教育の実践という話題も提供された。ポスター会場は24時間開放され、参加者同士の自由な議論が深夜・明け方まで続いた。
2023-思考院-7007 『数学を用いる生物学:理念・概念と実践・方法論』
数学を用いて生物について知ろうとする点で、数理生物学の数理モデルも生物データの統計モデルも、似たようなイメージを抱かれがちである。 しかし、両者は方法論だけでなく、そもそもの発想から異なっている、さらに、その違いが周知されていないため、あちこちで混乱が派生するという時代が20年以上続いている。 そんな状況を鑑み、本ワークショップでは、2023年8月28-29日、統計数理研究所第1セミナー室にて、口頭による話題提供と会場内でのポスター掲示を行ない、計58名の参加があった。 口頭による話題提供はいわゆる講演会とはほど遠い状態で、質疑の量は他に類例ないほど多く、用意したスライドの2/3しか披露できずに終わる場合もあった。 学生からの質問も多く、講演者の役割は、文字通り話題提供であり、それをネタに参加者が質疑や議論を交わすワークショップとなった。 話題提供の合間には、ポスター周辺で若い参加者同士の議論が繰り広げられた。夕方の終了後もポスター周辺で夜8時過ぎまで際限なく続いた。 口頭による話題提供は30代―40代を中心に企画したが、修士課程の学生や退官した教員も含めた。参加者は「育成される側」という意識で参加しており、 講師に数学を教わる場でなく、対等な研究者として生き物について考える場を志した。
2023-思考院-7008 『連続最適化および関連分野に関する夏季学校』

2023 年 8 月 9 日から 11 日にかけて, 統計思考院公募型人材育成事業として, 連続最適化および関連分野に関する夏季学校が開催されました. 本夏季学校は, 連続最適化とその関連分野における基本的な事項から最先端の動向までを整理・理解し, 学生を含む若手研究者の基礎力の養成および新たな研究テーマの発見を目的として 2021 年から開催しているものです. 今年は講師として東京大学の佐藤峻先生と統計数理研究所の Prof. Bruno F. Lourenço をお招きして, それぞれ連続最適化への応用に向けた常微分方程式の数値解析入門, A Conic Smörgåsbord と題した講義と演習をしていただきました. また, 現地会場での演習やポスターセッションでは参加者同士の議論が盛んに行なわれました. 現地参加は遠隔参加よりも大きな効果があるように思います. 一方で, 遠隔参加は気軽に参加できるという長所もあります. 現地と遠隔を合わせて 86 名と多くの方にご参加いただくことができました.
2023-思考院-7009 『第18回Biostatisticsネットワーク』
2023年8月18日・19日に「第18回Biostatisticsネットワーク」を北海道大学医学部学友会館フラテホールにて現地開催した。本行事は、医療統計学を専攻する国内の大学院生の研究交流を目的として毎年行われており、 今年は大阪大、大阪公立大、北里大、京都大、久留米大、東京大、東京医科大、東京理科大、東北大、北海道大、横浜市立大の11大学から教員と学生合わせて92名の参加があり盛会となった。 本会の大きな特徴は、準備や運営も各参加大学からの学生委員が主体となって行い、その過程でも交流が深められるという点にある。 今回は5つのセッションにおいて各大学の大学院生から、臨床試験方法論、統計的因果推論、医療データベースを用いた実データ解析など多彩な内容の研究発表があり活発な討論がなされた。 また2日目最後は北海道大学 横田勲先生による特別講演「君たちは生物統計とどう生きるか」を実施した。
2023-思考院-7010 『非可換確率論的ランダム行列の応用Non-Commutative Probability Theory, Random Matrix Theory and their Applications(NPRM2023)』

一つ目の話題はJorge Garza Vargas(カリフォルニア工科大学)による3回にわたるレクチャーで氏の普遍被覆木上の周期作用素についての講演で非可換確率論的にも計算機科学的にも面白い話題で多くの議論がなされた。 Ping Zhong氏の講演は参加者らの多くが研究している非エルミートランダム行列の固有値分布の話であり、大学院生の関連研究発表とも大きな相乗効果があった。江崎・薮奥氏の行列値ブラウン運動の固有値の挙動の話、早瀬氏の機械学習理論と非可換確率論の研究は学生や若手にとってその分野を知る用意きっかけを提供し、今後の関連研究への参加を促すことにつながったと思われる。 全体として会場内で多くの質問や個別議論が始まり、全参加者にとって刺激的な時間を提供できたのではないかと思う。実際この研究会の後継続して共同研究や個別の相談などをしている話を複数聞いている。共同研究を継続、事業参加の学生が複数名first authorとしての論文を完成させた。一つはすでに掲載されている。